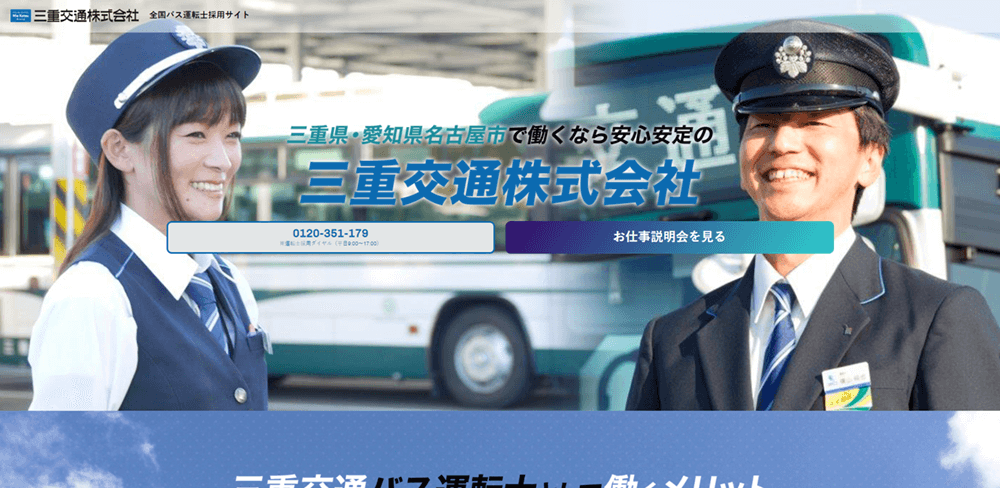バス運転手の眠気対策
このページでは、バス運転手があらかじめ講じておくべき眠気対策について、わかりやすく解説しています。個人で実行可能な対策例やバス会社がおこなっている眠気対策などをみていきましょう。バス運転手への転職を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
眠気対策でできること
バスの運転手にとって、居眠りをすることのないようしっかりと眠気対策をしてから業務にのぞむことがとても重要です。眠気対策にはどのようなものがあるでしょうか。
充分に体を休めておく
基本的なことかもしれませんが、身体の疲れを取り除いておくことが、そのまま眠気対策となります。運転中に眠気におそわれることのないよう、睡眠や休憩をしっかりと確保するようにしましょう。特に、夜行バス運転の場合は、昼夜逆転生活となるため、上手に睡眠をとるのが難しいこともあります。そんなときには、たとえ眠ることができなくても体を横にして休みをとることが大切です。
ガムも眠気対策になる
ガムを食べることも眠気対策になります。大型トラックの運転手であれば、大音量で音楽をかけながら運転して眠気対策としている方もいますが、乗客を運んでいるバス運転手ではできません。けれどもガムを食べて眠気を覚ます方法であれば、迷惑をかけることもないでしょう。
仮眠後にカフェインを摂取する
眠気覚ましとして30分間を超える長さの仮眠をとった場合、「睡眠慣性」という、ある意味「寝ぼけた状態」がしばらく続きます。ですので、長い仮眠のあとは、なんらかの方法で脳を覚醒状態へと戻す必要があります。身体を動かしたりする以外に、カフェインの摂取もおすすめです。ただ、カフェインの効果が発揮されるまで15~30分のタイムラグがあるので、その点には注意が必要です。タイムラグを計算に入れてコーヒーなどを飲むようにしましょう。
バス会社が行う眠気対策
バス運転手が個人で実践できる眠気対策もありますが、会社側がおこなっている眠気対策もあります。
危険を知らせる装置を導入
バス内には、バス運転手の居眠りを防止するための、様々なハイテク装置が設置されています。例として「ドライバーステータスモニター」が挙げられます。これは、居眠りや脇見運転などが検知されると、音声や警報でそのことを伝えてくれる装置です。ほかにも、車線を逸脱すると警報が作動する装置などもあります。
警報音は、乗客にとって心地よいものではないですが、安全を優先して考えるべきであるという判断のもと、装置を導入する会社が増加しつつあります。
勤務スケジュールに充分な休憩時間を組み込む
人手不足が深刻化してきているなか、それでも安全のために、運転手の充分な休息時間を確保することを重視する会社もあります。また、「疲労ストレス計」を導入し、一定の基準をオーバーしている場合には、その運転手をその日のシフトから外すようにしているところもあります。
運転手の居眠りで起きた事故
居眠りによる事故も多く起きています。その1つが、過去に群馬県藤岡市関越自動車道上り線で起きました。藤岡ジャンクション付近で高速ツアーバスが事故を起こした事例です。乗客は45 名で、道路の左側壁に衝突して乗客7名が亡くなり、38名が重軽傷を負ったという事故でした。
原因として運転手は「居眠り」と述べているようです。運営会社への立入検査で、日雇い運転者の選任、運行指示の不実施、運転者の健康や、注意事項伝達の点呼の不実施などがわかりました。他にも運行管理が不適切、車両の整備不良など多数の違反が確認されたようです。
安全対策強化が実施された
上記、関越自動車道での高速ツアーバス事故を受け、国土交通省では事故対策本部の設置と情報収集を実施しています。同時に緊急対策として過労運転防止のための交代運転者配置基準の明確化と厳格化、平成26年度末までの2年を期間とする、高速、貸切バスの安全、安心回復プランによる安全対策強化を実施しました。
内容は、新高速乗合バスへの行こうと一本化や貸切バスの安全性向上、安全優先経営の徹底、ビジネス環境の適正化と改善です。
法令遵守の徹底・悪質事業者の排除
緊急重点監査の結果、高速ツアーバスを運行する事業者の中には、重大な違反をしているケースも見受けられました。そういった悪質事業者の排除として、重大な違反が疑われるような事業者のリストが公表されました。
過労運転の防止
関越道の事故の大きな原因として考えられるのが運転手の居眠りです。運転中でも居眠りをした原因として、過労運転が挙げられます。そのため、長距離、夜間運行をする高速ツアーバスに対し、ワンマン運行できる時間と距離の上限を定めた、交替運転者の配置基準を策定しました。
旅行業者・貸切バス事業者間の取引環境の整備
旅行業者と貸切バス事業者の間で取引内容の明確化と公正な取引の確保のため、運送に関する文章の作成と保存を義務つけた施策です。
利用者への情報提供
利用者が事業者の安全性を確認できるような情報を表示するようになりました。目的は利用者が適切な高速バスを選択できる環境を整備するためです。旅行業者は、高速乗合バスと高速ツアーバスの交替運転者の配置状況などの情報を表示するように指導をはじめました。
もしナルコレプシーになったら
公共交通を担うバス運転手は、多くの人命を預かる重要な職業です。しかし、その運転手がナルコレプシーを発症した場合、どのように対処し、何に注意すべきなのでしょうか。
ナルコレプシーとは何か
ナルコレプシーは、日中に極度の眠気を感じる、または突然意識を失って眠りに落ちるという症状を特徴とする慢性的な神経疾患です。特に以下のような症状が問題となります。
- 過度の日中眠気:日中に眠気が抑えられず、通常では考えられない状況で眠りに落ちることがある。
- 情動脱力発作(カタプレキシー):笑う、驚くなどの強い感情の変化が引き金となり、一時的に筋力が失われる。
- 睡眠麻痺:目覚めや入眠時に体が動かせなくなる。
- 入眠時幻覚:睡眠に入る直前に鮮明な幻覚を見る。
これらの症状は運転中に発生すると、重大な交通事故につながる危険性が極めて高いため、ナルコレプシーを発症した運転手が治療無しでそのまま業務を続けることはできません。
バス運転手としてのリスク
職業運転手としての特有の責任
バス運転手は、大型車両を運転し、多数の乗客を安全に目的地まで運ぶ役割を担います。そのため、運転中の体調不良や注意散漫は、以下のような重大な結果を招く可能性があります。
- 重大事故:ナルコレプシーの発作で一瞬でも意識を失うと、多くの人命を危険にさらします。
- 社会的影響:公共交通機関での事故はニュースで大々的に報道され、会社の信用にも関わります。
ナルコレプシーが疑われた場合の対応
早期の診断と専門医への相談
ナルコレプシーの症状が疑われる場合、早急に睡眠専門医に相談し、正確な診断を受ける必要があります。診断には次のような検査が用いられます。
- ポリソムノグラフィー(睡眠検査):睡眠中の脳波や心拍数を記録する。
- MSLT(多相性睡眠潜時検査):日中にどれだけ早く眠りに入るかを測定する。
これらの検査を通じて、ナルコレプシーであるかどうかが明らかになります。
企業への報告
バス運転手がナルコレプシーの診断を受けた場合、まずは雇用主に報告する義務があります。適切な対応を取らなければ、事故のリスクが高まり、さらには法律違反となる可能性もあるためです。
治療と管理
薬物療法
ナルコレプシーの治療は主に薬物療法が中心です。以下の薬が使用されることがあります。
- 中枢神経刺激薬:日中の眠気を軽減する。
- 抗うつ薬:情動脱力発作の予防に使用される。
- 睡眠薬:夜間の睡眠を安定させる。
ライフスタイルの改善
薬物療法に加え、ライフスタイルを改善することも重要です。特に以下の点に注意する必要があります。
- 規則的な睡眠スケジュール:毎日同じ時間に寝起きする習慣をつける。
- 昼寝の取り入れ:短時間の昼寝を取り入れることで眠気を抑える。
- ストレス管理:過度なストレスは症状を悪化させるため、適切に管理する。
運転免許と法的規制
運転免許の取得・更新に関する規定
日本では、ナルコレプシーを含む睡眠障害を持つ者が運転免許を取得・更新する場合、医師の診断書が必要です。診断書には、症状が運転に支障を与えないことが記載されていなければなりません。
診断書提出の重要性
診断書を偽装する、または提出しない場合、以下のような法律違反に問われる可能性があります。
- 道路交通法違反:安全運転義務違反として罰則が科される。
- 労働契約違反:企業規則に違反し、解雇理由となる可能性がある。
企業の対応と再就職の選択肢
職場での対応
企業側は、運転業務から離れることを前提に適切な職務転換を検討するべきです。
- 事務職や運行管理職への配置転換:運転を伴わない仕事への異動。
- 休職制度の利用:治療に専念する期間を設ける。
再就職の可能性
症状が重くバス運転手としての復帰が困難な場合、別の分野での再就職を検討する必要があります。運輸業界には、運行管理や教育指導など、運転以外の職種も多く存在します。
ドライバーの異常を検知するシステムの例
事故対策のためのドライバーの以上を検知するシステムも登場しています。バス利用者と運転手を守るためにも導入したほうがいいでしょう。
ガーラ(いすゞ)
衝突被害軽減ブレーキシステムを提供しています。ミリ波レーダーと画像センサーを組み合わせて、歩行者や低速走行車を検知する仕組みです。追突の危険性があると、早期にドライバーへ警報とディスプレーで通知します。また、早期の警報音と弱いブレーキ作動を実施し注意喚起するのもポイントです。さらに追突の可能性が高まった場合、強い警報と本格制動を作動し衝突を回避します。危険回避が行えない場合でも、強いブレーキが作動して追突被害を軽減するシステムです。他にも可変スピードリミッターで車間距離の自動的な維持、オートハイビームや車間距離警報装置や車両安定制御システムを提供しています。
ドライバーモニター
走行時、ドライバーの運転姿勢や顔向きやまぶたの開閉状態をモニターする装置です。前方注意力不足を検出したときは、警報音と警告表示により注意喚起します。わきみや居眠り運転防止に役立つでしょう。
ドライバー異常時対応システム
事故の原因として、ドライバーの突発的な病気というケースがあります。急病のような異常が発生すると、ドライバーや乗務員がスイッチを押すことで車両は制動を実施するシステムです。客席上部にも客席スイッチが備わっています。制動がスタートし、非常ブザーが鳴り、客席スイッチ内蔵ランプと赤色フラッシャーが点滅することで乗客に異常を通知できるのです。車外にもホーンやストップランプとハザードランプの点滅で周囲に異常を知らせます。EDSSスイッチが押されなくても、ドライバーモニター機能により異常を検知。車両が走行車線からはみ出したら、車線逸脱警報が作動し、速度を徐々に落として停止します。
対策を徹底している会社を選んだほうが良い
バス運転手として働くということは、乗客の命も守らなければなりません。そのためにはバス運転手は健康管理への意識も必須です。バス会社の中には、利益優先でバス運転手に無理をする悪質業者も存在します。悪質な会社で働くとなると、過労や整備不良で大事故が起きかねません。一旦事故が起きてしまえば、業者だけではなく運転手の責任も追及されかねないです。
そのような業者で働くより、体調管理の対策をしっかりしているところを選んだほうがいいでしょう。対策を徹底しているバス会社ならその不安も解消されるはずです。
眠気の原因は改善しておいたほうが良い
さまざまな眠気対策についてみてきましたが、人によって、体質に合う眠気覚ましの方法は異なります。ですので、自分に適した方法を見つけるために、いろいろと試してみることをおすすめします。また、乗客の安全を確保しつつ業務を遂行するために一番重要なのは、眠気の原因自体を、できるだけつくらないようにすることだと言えます。休めるときにはしっかりと休むことが重要です。
愛知でバス運転手として働ける会社を見る